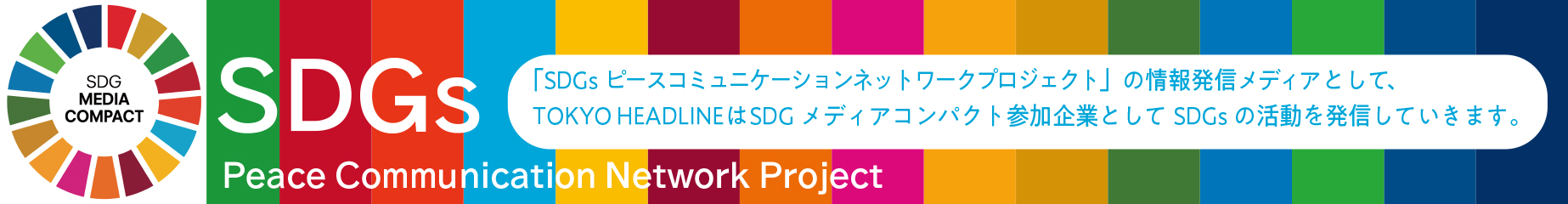小学生が愛媛・松山市の未来をテーマに白熱プレゼン! ポイントは「思いやりの循環」 〈国連を支える世界こども未来会議 in MATSUYAMA〉

小学生が自分たちが暮らす地域の未来の姿を考える「国連を支える世界こども未来会議 in MATSUYAMA」が2月1日、愛媛・松山市の松山区役所で開催された。イベントには、市内の小学校の4~6年生約50人が参加し、SDGs(持続的な開発目標)の達成の観点から「住み続けられる未来の松山市」をテーマに、約4時間にわたって意見交換し、アイデアをまとめた。
イベントはワークショップとプレゼンテーションで構成。子どもたちはランダムにA~Jまで10のグループに振り分けられ、それぞれのグループ内で意見を交換して提案をまとめ、プレゼンテーションを行った。
ワークショップでは、“わたしたち”のよりよい在り方を可視化する『わたしたちのウェルビーイングカード』(NTT)を活用。〈社会貢献〉〈緑〉〈平和〉〈希望〉〈応援・推し〉といった、自分らしく、いきいきと生きるあり方や、心地よくいられる状態を示す「ウェルビーイング」を感じる言葉が書かれたカードで、児童たちは自分がいきいきと生きるために必要なものを選び、選んだ理由を説明しながら自己紹介、そこから「住み続けられる未来の松島市」へと考えを広げていく。

各グループで、ゴミ問題、人口の流出、観光の促進、交通の整備など松山市が抱えているさまざまな問題を出しあうと、大学生などのコミュニケーションサポーターの助けを借りながら、「住み続けられる未来の松山市」を実現するためには解決する必要がある問題は何か、そのために自分たちが明日からできることは何かを具体的に考えた。
プレゼンテーションでは約3分間の持ち時間をフルに活用し、自然や環境を守る方法、価値観の理解を促進するアイデア、給食の食べ残しを活用した取り組みなど具体的な施策も含め発表。日本のなかでも多くの人が知る観光地であることもあって、松山市の魅力を発信するものや観光客や松山市を訪れる人を巻き込んで行う取り組みの提案が多かった。また手作りイベントからアプリ、メタバースを活用した取り組みまでさまざま。プレゼンテーションが進行するほどに、他グループの参加者たちからの質問も多くなり、予算に関わる問題など鋭い質問も出て、松山市の野志克仁市長ら審査員や保護者ら大人たちを苦笑いさせた。