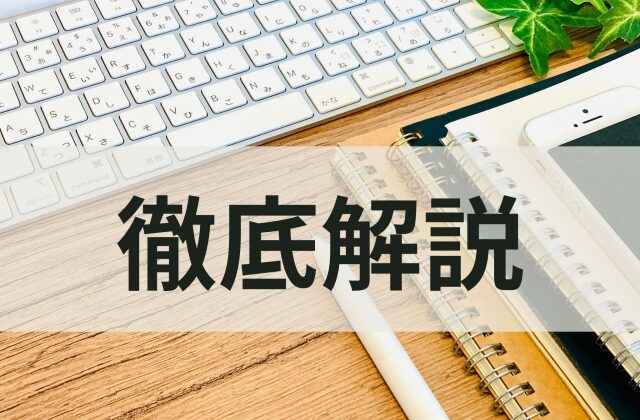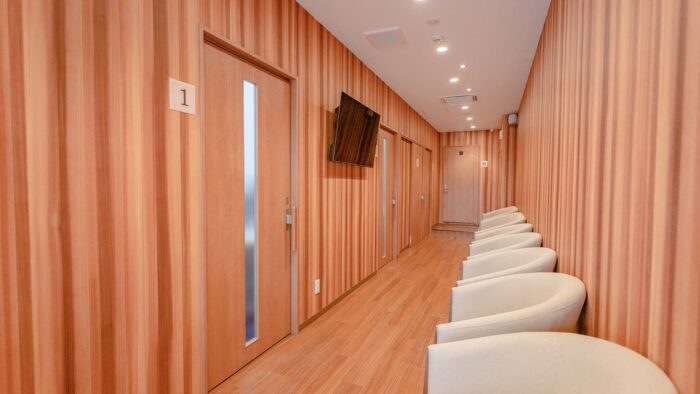糖尿病とは?基本的な理解
糖尿病は膵臓から分泌されるインスリンの作用不足により、血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が慢性的に高くなる状態です。高血糖が続くと、全身の血管や神経に障害が生じ、様々な合併症を引き起こす可能性があります。
糖尿病の怖さは、初期には自覚症状がほとんどないため、健康診断で指摘されても放置してしまうケースが多いことです。また、一時的に血糖値が改善したからといって治療を中断すると、気づかないうちに合併症が進行してしまうこともあります。
糖尿病の主な症状
糖尿病は初期段階では自覚症状がないことが多いですが、血糖値が高い状態が続くと、以下のような症状が現れることがあります。これらの症状がある場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
- 喉の渇きが異常に強くなる(口渇)
- 尿の量が増え、特に夜間の頻尿が目立つ(多尿)
- 食べているのに体重が減少する
- 逆に急激な体重増加がみられる
- 全身の倦怠感や疲れやすさを感じる
- 手足のしびれや痺れ感がある
- 足のむくみが気になる
- 立ちくらみが頻繁に起こる
- 傷の治りが遅い、または痛みを感じにくい
- 視力の低下を感じる
また、家族歴(両親や兄弟に糖尿病患者がいる)も重要なリスク因子となります。これらの症状や状況に心当たりがある方は、血糖値の検査を受けることをおすすめします。
糖尿病の原因とメカニズム
糖尿病の発症には「インスリン」というホルモンが深く関わっています。インスリンは血糖値を調節する重要な役割を担っていますが、このインスリンの分泌量が減少したり、働きが低下したりすることで糖尿病が発症します。
インスリンの役割
私たちが食事をすると、摂取した栄養素はブドウ糖などに変換されて血液中に流れ込みます。この血糖値の上昇を感知すると、膵臓のβ細胞からインスリンが分泌されます。
インスリンには主に次の働きがあります。
- 血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓などの細胞内に取り込ませる
- 余分なブドウ糖をグリコーゲンや中性脂肪として蓄える
- 肝臓での糖新生(アミノ酸などから糖を作り出すこと)を抑制する
これらの働きにより、血糖値が適切な範囲に保たれています。しかし、インスリンの分泌量が少なかったり、インスリンの効きが悪くなったりすると(インスリン抵抗性)、血液中にブドウ糖があふれ、高血糖状態となり糖尿病が発症します。
糖尿病の症状に心当たりがある場合や、治療について詳しく知りたい方は、専門の管理栄養士が在籍している「初台まちのクリニック」
糖尿病の主なタイプ
糖尿病は大きく分けて「1型糖尿病」と「2型糖尿病」の2つのタイプに分類されます。それぞれ発症メカニズムや特徴が異なります。
1型糖尿病の特徴
型糖尿病は、インスリンを作る膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなることで発症します。日本における糖尿病患者全体の約5%と比較的少数です。
主な特徴:
- 主に小児や若年層に発症することが多い
- 自己免疫疾患の一種で、ウイルス感染などが引き金になることがある
- 急激に進行することがあり、特に「劇症1型糖尿病」では発症から1週間以内に生命に関わる状態になることも
- インスリン治療が不可欠
1型糖尿病は生活習慣とは直接関係なく発症するため、予防が難しい疾患です。早期発見と適切なインスリン治療が重要になります。
2型糖尿病の特徴
2型糖尿病は日本の糖尿病患者の90%以上を占める最も一般的なタイプです。インスリンの分泌量の低下とインスリン抵抗性の両方が原因となって発症します。
主な特徴:
- 主に40代以降に発症することが多い
- 遺伝的要因と生活習慣が深く関わっている
- 過食、運動不足、肥満(特に内臓脂肪型肥満)が主なリスク因子
- ストレス、睡眠不足、過度の飲酒、喫煙なども発症リスクを高める
日本人は欧米人に比べてもともとインスリンの分泌量が少ないと言われており、肥満でなくても糖尿病を発症するリスクがあります。これが「やせ型の糖尿病」と呼ばれるものです。
2型糖尿病は生活習慣の改善によって予防や症状の改善が可能な場合が多いため、バランスの良い食事や適度な運動を心がけることが重要です。
糖尿病の合併症
糖尿病の最も怖い点は、高血糖状態が続くことで様々な合併症を引き起こすことです。特に「三大合併症」と呼ばれる重篤な合併症は、生活の質を大きく低下させる原因となります。
糖尿病の三大合併症
長期間の高血糖状態により、全身の細い血管や神経に障害が生じることで、以下の三大合併症が発症します。
糖尿病網膜症
網膜の血管が障害されることで起こる眼の病気です。初期には自覚症状がほとんどありませんが、進行すると網膜出血や網膜剥離を起こし、視力低下や最悪の場合は失明に至ることもあります。
日本における失明原因の第2位とされています。糖尿病と診断されたら、定期的な眼底検査が必要です。
糖尿病腎症
腎臓の糸球体という部分の毛細血管が障害され、腎機能が徐々に低下していく病気です。初期には尿タンパクの増加などの軽微な変化から始まりますが、進行すると腎不全となり、人工透析が必要になることもあります。
日本で透析治療を受けている方の約3分の1は糖尿病腎症が原因とされています。
糖尿病神経障害
高血糖による神経細胞の障害や、血管の変化による神経への栄養供給低下によって起こります。初期には手足のしびれや痛み、感覚異常などの症状が現れ、進行すると感覚が鈍くなり、怪我や火傷に気づかないこともあります。
また、自律神経にも影響し、立ちくらみ、発汗異常、胃腸障害、排尿障害、勃起障害などの症状も現れることがあります。
その他の合併症
三大合併症以外にも、糖尿病は様々な合併症を引き起こします。
- 大血管障害(動脈硬化):心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まる
- 認知症:血管性認知症やアルツハイマー型認知症のリスクが上昇
- 歯周病:歯周病が悪化しやすく、逆に歯周病が血糖コントロールを悪化させることも
- 感染症:免疫機能の低下により、感染症にかかりやすく、重症化しやすい
- 骨粗しょう症:骨密度の低下が起こりやすい
これらの合併症は、適切な血糖コントロールによって予防や進行を遅らせることが可能です。そのため、糖尿病と診断されたら、定期的な検査と適切な治療を継続することが非常に重要です。
まとめ
糖尿病は初期には自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行してしまうことが多い病気です。しかし、高血糖状態が続くと、網膜症、腎症、神経障害などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
糖尿病の症状に心当たりがある方や、健康診断で血糖値の異常を指摘された方は、早めに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることをおすすめします。また、2型糖尿病はバランスの良い食事や適度な運動などの生活習慣の改善によって予防や症状の改善が可能な場合が多いため、日頃から健康的な生活を心がけることが大切です。
糖尿病は一度発症すると完全に治すことは難しい病気ですが、適切な治療と生活習慣の改善によって、合併症の発症や進行を防ぎ、健康的な生活を送ることが可能です。